第2章の1 家を建てるときの流れ
・相談からプラン作成まで
家を建てるときに、誰でも自分たちがどのように住みたいか考えます。しかしそれを具体的な形にする作業は専門的な知識も必要とされます。
自分の建てたい家を思い浮かべる為にハウスメーカーのモデルルームを見たりして、イメージを膨らましていくわけですが、なかなか自分の土地にどのような建物を建てることが可能で、どのような住まい方をするのかを考えることは難しいものです。
多くのハウスメーカーでは、このような段階の相談やプランの作成などはサービスとして無料で行っているようです。サービスでやってくれるので、複数のハウスメーカーに依頼してそれを比較して検討する人も多いようです。 しかしそれぞれのハウスメーカーに自分が家を建てる意志があり予算はどの程度なのかを知らせるわけですから、当然営業担当者は熱心に営業活動を行うようになります。
一方、建築設計事務所に相談した場合、簡単な相談だけで相談料を取られることはまずありませんが、ハウスメーカーが無料で作ってくれるようなプランを作成するだけでも費用がかかる場合があります。相談をする前に念のために確かめる方が良いでしょう。
それではなぜハウスメーカーが無料でできることが建築設計事務所では有料になるのでしょうか。それは後の「設計料」の章でもう少し詳しく見ていきます。
この段階では家を建てる予定の敷地の大きさや形状、方位などを確認し、建築基準法などの法律と照らし合わせて検討を行います。当然のことですがプランづくりは、家を建てる中でとても重要な事柄のひとつです。
この段階でこれから何十年と住むことになる空間が良くも悪くもなります。何十年の時間と空間をバタバタと1週間や2週間で決めてしまうことにならないように、じっくりと時間をかけて相談・検討をしてもらいたいと思います。
建築設計事務所に設計を依頼される場合には、遅くてもプランが完成するまでに設計監理契約の話をしておく必要があります。建築主にとってもいくら設計料がかかるのか分からないままで設計が進んで行けば不安な気持ちになります。
ここはなあなあではなく、はっきりと書面で設計監理契約をすることで、お互いの立場を明確にして気持ちよく作業を進められる環境をつくることが大切です。
・建築確認申請
プランが固まってきますと、役所に提出する建築確認申請の準備を進めます。建築確認申請で必要な図面は、平面図や立面図、断面図など基本的な図面だけですので、プランが決まっていて外壁の仕上げなどが決まっていれば比較的容易に準備することができます。しかし建物の構造が木造3階建てであったり、コンクリート造や鉄骨造である場合はより詳しい構造計算書が必要になりますのでもう少し時間がかかります。
またこの時期には、プランを作成するだけではなく、安全な建物を建てるために地盤の確認なども行います。軟弱な地盤の場合には建物を建てる費用に占める基礎関係の工事費用が大きくなる場合もありますので、慎重な調査が必要になります。この調査に基づいて建物の基礎形状や地盤改良の要不要を判断します。
一部の業者ではこの段階の図面で「見積書」と称する書類を作成して、建築工事請負契約を締結する場合があるようです。
ハウスメーカーなどでは、請負契約の前に設計契約を別に行うことはまずありませんから、無料で行っていた設計の作業が完了するとなるべく早い段階で請負契約をしようとする傾向があります。
一部のハウスメーカーでは、部材がコンピュータに登録されていて、この時点でもオプションで取り付く部材や、窓やドアの仕様、仕上げが分かればそれなりに正確な見積を作ることができる体制が取られているところもあるようです。
しかし、建物本体は比較的決められた部材でつくることができるため、正確な見積が可能になるのは分かるのですが、実際には基礎や地盤改良、外構工事などその土地の状態によって大きく異なる部分の見積は、詳しい図面がないこの時点では正確な値段を出すことは困難だと思われます。
通常の設計では、平面図や立面図程度しか無い状態では、正確に見積を作成することは不可能です。 住宅金融公庫から建築資金の借り入れを考えている方も多いでしょう。公庫の建築基準の審査も建築確認申請と同時に提出します。実際には、住宅金融公庫の設計審査も建築確認申請と同じ部署で審査を受けることになります。
ハウスメーカーや工務店に設計の段階から依頼しても実際に建築確認申請を行うのは、資格のある建築設計事務所になります。
そのために建築主は建築確認申請の申請書、「建築確認申請の提出のため」の代理人への委任状や「工事監理者の選定届け」に捺印することになります。この時に建築工事が始まってから問題になる「工事監理者の届け」もほとんどの場合同時に提出されます。
ハウスメーカーでは代理人は外注の設計事務所、設計者と現場監理者はハウスメーカーが登録している事務所の管理建築士の名前が記載されることが多いようです。(もちろんハウスメーカーも建築設計事務所登録を行っています)
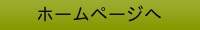



 第1章
第1章